この記事は前回の記事からの続きになります。

前回の記事では、
育毛のためには、頭皮の毛細血管の血流量が重要
↓
血流を増やすためには、胃腸の働きが大事
↓
胃腸の働きを良くするためには、
朝食をとる、夕食を食べすぎない、よく噛んでゆっくり食べる
ことが重要だとお伝えしました。
今回も胃腸に良く、血液を作りやすい体づくりをするための食事法をお伝えします。
Contents
血液たっぷり対策その4~主食はパンよりもごはんを食べる~
ごはんやパンに含まれる栄養素である炭水化物は、消化・吸収されるブドウ糖(血糖)に変わり、体や脳を動かすエネルギーとして消費されます。
パンとごはんを食べた後に血糖値を測ってみると、ごはんはゆっくりと上昇して下降していくのに比べて、パンは急激に上昇して、急降下します。
このような血糖値の大きな変動は、すい臓に負担をかけてしまいます。
血糖値の急激な上昇は肥満につながります。血糖値が上がるとインシュリンというホルモンが分泌され、インシュリンが血糖中の糖を取り込んでエネルギーを消費します。
血液たっぷり対策その5~体を温める食材を食べよう~
昔の人は、夏は体から熱を逃がす食材、冬は体を温める食材を上手に食事に取り入れて、体温を調整していました。
現代の冷房に頼る生活では、夏でも冷えている人が多いですから、常に体を温める食事が重要になっています。
体を温める食材は、寒い地域が原産地で秋冬が旬、水気が少なく、赤や黒など色が濃いもので、地下に伸びて生育するものです。
逆に体を冷やす食材は、暑い地域が原産地で春夏が旬、水気が多くて色が薄いものです。
ただ、体を冷やす食材でも、加熱すれば温める食事になります。
同じものばかりではなく、工夫していろいろな食材を食事に取り入れることが大切です。
血液たっぷり対策その6~スパイス&香味野菜&発酵食品で体を温めよう~
体を温める食材を選ぶ際に、さらに効果を高めるためのポイントが3つあります。
1つ目はスパイスです。唐辛子やターメリック、シナモン、コショウ、ナツメグ、山椒は料理に積極的に利用することで、温め効果がアップします。
特に唐辛子に含まれるカプサイシンは、熱生産を促進して体温を上げる働きがあるほか、胃液の分泌も促して消化・吸収を助けてくれます。
2つ目は、しょうがや大葉、ねぎ、ニラ、にんにくなどの香味野菜です。
しょうがに含まれる辛み成分の1つであるショウガオールには、血流を促進して体を温める効果があります。
料理に使うのはもちろんのこと、温かい飲み物のの1つとしてしょうが湯もおすすめです。
3つ目は納豆や味噌、漬物などの発酵食品です。
発酵食品は体を温めるだけではなく、胃腸の調子も整えます。
中でも大豆は「畑の肉」と言われるように、血を作る大事な栄養素であるタンパク質が豊富に含まれているほか、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きを持つイソフラボンも含まれており、抗酸化作用があるため育毛に効果的です。
血液たっぷり対策その7~血の質を高めるために鉄とタンパク質を摂取しよう~
鉄は赤血球のヘモグロビンの構成要素として重要な栄養素です。
酸素は赤血球にくっついて運ばれていきますが、血液中の鉄が足りなくなると鉄欠乏性貧血となり、体内に酸素を十分に運べなくなるため注意が必要です。
またたんぱく質も大事な栄養素になります。たんぱく質の摂取量が減れば、血の質はすぐに悪化してしまいます。
スーパーやコンビニのお惣菜やお弁当などの外食が続いている人は、野菜やたんぱく質が不足しないように注意が必要です。
きな粉牛乳をお風呂上がりに飲むのが習慣になっています。
血液たっぷり対策その8~冷たい飲み物は避けよう~
冷たい飲み物は体内の温度を一気に下げます。
冷蔵庫で冷えた飲み物は約4度、私達の体内はおよそ37度であるため、これだけ温度差のあるものが一気に体内に流し込まれます。
低下した体内の温度をもとに戻すのは6000キロカロリー必要で、もとの温度に戻るには時間がかかります。
そのため冷たい飲み物をできる限り控え、普段から暖かい飲み物や常温の飲み物を取るように心がけましょう。
内臓や腸の負担を軽減できます。
6000キロカロリーは、もう少し精査が必要かもしれませんが
成人男性の1日の必要カロリーが2200カロリー程度なので、冷えがいかに体に負荷を与えるかが分かりますね。
まとめ
食べ過ぎも冷えも血液たっぷりの肝である、胃腸の働きを悪くしちゃうのですね。
⭐️少食だからこそ食事の質にはこだわろう!⭐️
おすすめの関連記事



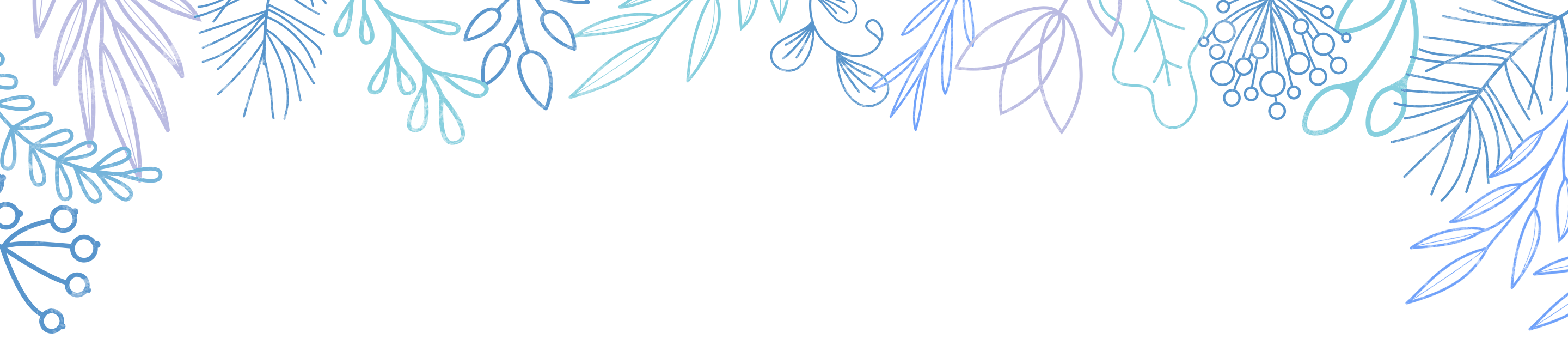
















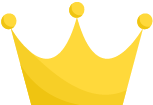 馬油シャンプー(アズマ商事)
馬油シャンプー(アズマ商事) 
 Le ment -sparkling oil cleansing & shampoo -
Le ment -sparkling oil cleansing & shampoo - 
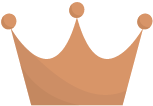 薬用ヘアシャンプー(株式会社ルチア)
薬用ヘアシャンプー(株式会社ルチア) 